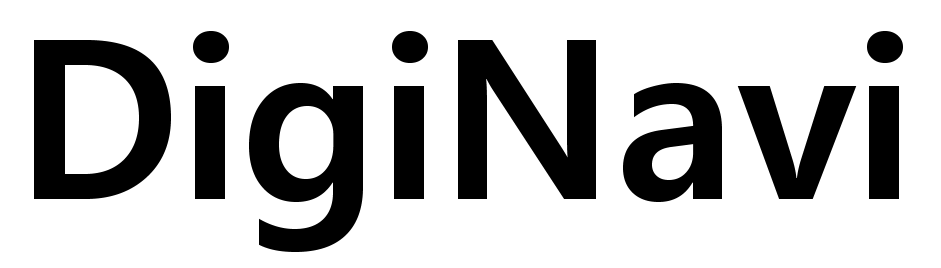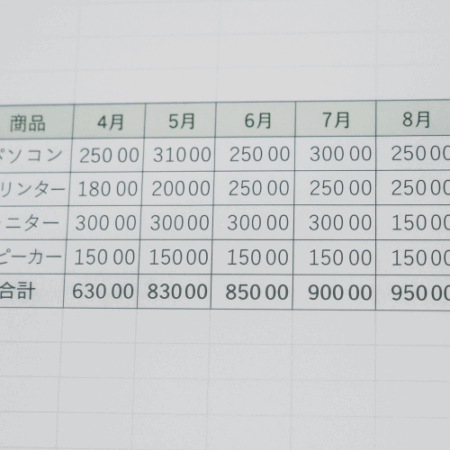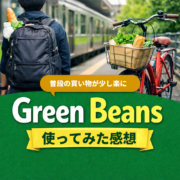【初心者向け】パソコンの「CPU」ってなに?“頭脳”の役割、性能の見方、選び方をやさしく解説!

「このパソコン、CPUはどれくらいの性能なんだろう?」
「友達が『Core i5が良いよ』って言ってたけど、よくわからないな…」 「カタログに書いてある『CPU』って、何を見ればいいの?」
パソコンのカタログを見たり、誰かに相談したりした時に、「CPU」という言葉を耳にしたことはありませんか?
CPUは、例えるならパソコンの「頭脳」や「心臓」とも呼ばれる、とっても大切な部品です。 このCPUの性能で、パソコンの「サクサク動くか」「同時に色々な作業ができるか」といった快適さが大きく変わるんです。
この記事では、パソコンの仕組みが苦手な方でも大丈夫!
- CPUがどんなお仕事をしているのか(パソコンの「頭脳」として何をしているの?)
- 「Core i〇」や「Ryzen〇」といった名前や数字の意味(どれがすごいの?何が違うの?)
- あなたの使い方に合ったCPUの選び方(動画を見たり、書類を作ったり…自分にはどれが合ってる?)
- 意外と重要!「世代」の見方(新しいCore i5が古いCore i7より速いってホント?)
などを、難しい言葉を使わずに、イラストや例えを交えながらやさしく解説していきます。
この記事を読めば、CPUのことが分かって、パソコン選びや今お使いのパソコンの理解に役立つはずですよ。
◆ CPUは「パソコンの頭脳」!どんなお仕事してるの?
CPU(シーピーユー / 正式名称:中央演算処理装置)は、例えるならパソコンのすべての指示を処理する「とっても賢い脳みそ」です。
あなたがパソコンに何かお願いをする時(例えば、マウスでアイコンをクリックする、キーボードで文字を入力する、アプリを起動するなど)、その一つ一つの「命令」はすべてCPUに送られます。
そして、CPUはそれらの命令を受け取って、計算したり、判断したり、パソコンの他の部分(メモリやストレージなど)に指示を出したりする、という仕事をものすごい速さで行っています。
- アプリを開こうとクリックすると… → CPUが「アプリを起動せよ!」という命令を受け取って処理を始めます。
- キーボードで「あ」と入力すると… → CPUが「『あ』という文字を表示せよ!」という命令を処理し、画面に文字が表示されます。
- インターネットでWebサイトを見ると… → Webサイトのデータを処理して、画面に表示させるのはCPUのお仕事の一部です。
このように、CPUはパソコンが行うすべての作業の中心となって働いています。
このCPUの性能(頭の良さや計算の速さ)が高ければ高いほど、パソコンはたくさんの作業を同時にこなせたり、難しい計算を早く終わらせたりできるので、パソコン全体の動きが「サクサク」と快適になるというわけです。
先ほど解説した「メモリ(作業スペース)」が広いほど効率が上がるのと同様に、「CPU(頭脳)」の性能が高いほど、難しい作業も速くこなせます。 例えるなら、メモリは「机の広さ」、CPUは「机に向かう人の頭の良さや作業の速さ」といった関係性です。
◆ 「Core i〇」や「Ryzen〇」って?CPUの性能ランク

パソコンのCPUでよく見かける名前として、Intel(インテル)社の「Core iシリーズ」や、AMD(エーエムディー)社の「Ryzen(ライゼン)シリーズ」があります。 これらは、CPUの性能を分かりやすくランク分けしたものです。
| CPUのシリーズ・名前 | 簡単なイメージ | どんな人におすすめ? |
|---|---|---|
| Intel Core i3 | 基本の頭脳 | メール、インターネット検索、簡単な文書作成がメインの方 |
| Intel Core i5 | 標準的な頭脳 | 日常的な利用に加え、写真の軽い編集などもする方 |
| Intel Core i7 | 高速な頭脳 | ビジネスで複数のアプリを同時に使う方、簡単な動画編集もする方 |
| Intel Core i9 | 最高クラスの頭脳 | プロレベルの動画編集、最新の高画質ゲーム、専門的な作業をする方 |
| AMD Ryzen 3 | 基本の頭脳 | Core i3 と同様の使い方をする方 |
| AMD Ryzen 5 | 標準的な頭脳 | Core i5 と同様の使い方をする方 |
| AMD Ryzen 7 | 高速な頭脳 | Core i7 と同様の使い方をする方 |
| AMD Ryzen 9 | 最高クラスの頭脳 | Core i9 と同様の使い方をする方 |
基本的に、数字が大きくなるほどCPUの性能(頭の良さや計算の速さ)が高くなります。
これは、たくさんの命令を同時に処理できる「コア数」が多かったり、一つの処理を素早く終わらせる「動作周波数」が高かったりするためです。 (難しい名前ですが、「一度にたくさん考えられる」とか「素早くひらめける」頭脳、というイメージです)
ただし、このランク分けはあくまで「同じ世代の中での目安」である点に注意が必要です。 次に解説する「世代」が、性能に大きく影響するからです。
◆ ここが超重要!CPUは「世代」で性能が大きく変わる!
CPUを選ぶときに、「名前(Core i5とかRyzen 7とか)」と同じくらい、いやそれ以上に大切なのが、CPUの「世代」です。
CPUの技術は日々進化しているので、新しい世代のCPUは、古い世代のCPUよりも、同じランクの数字でも性能が大幅に向上していることがよくあります。
例えるなら、同じ「算数の得意な小学生(Core i5)」でも、今の小学生は昔の小学生より最新の計算ツール(電卓やPCなど)を使うのが上手なので、複雑な計算でも早く正確にできる、といったイメージです。 (ちょっと違うかもしれませんが…!)
実際にどんなことが起きる?
- 5年前に発売された「Core i7」よりも、最近発売された「Core i5」の方が、実際のパソコン作業がサクサク快適に動くということがよくあります。
- 古い世代のCPUだと、最新の重たいアプリがうまく動かなかったり、動いても非常に遅かったりすることがあります。
「世代」はどうやって見分けるの?
Intel Core iシリーズの場合:
- 型番は「Core i〇-〇〇〇〇」のような数字が続きます。
- ハイフンの後の最初の1桁または2桁の数字が「世代」を表しています。
- 例:Core i5-13400F → 第13世代 の Core i5
- 例:Core i7-12700K → 第12世代 の Core i7
- 例:Core i7-8700 → 第8世代 の Core i7(古い世代)
AMD Ryzenシリーズの場合:
- 型番は「Ryzen 〇-〇〇〇〇」のような数字が続きます。
- ハイフンの後の最初の1桁または2桁の数字が、おおよそ「世代」や「シリーズ」を表しています。
- 例:Ryzen 5-7600 → Ryzen 7000シリーズ(比較的新しい世代)
- 例:Ryzen 7-5700X → Ryzen 5000シリーズ(一つ前の世代など)
- 例:Ryzen 5-3600 → Ryzen 3000シリーズ(古い世代)
このように、CPUを選ぶ際は、「名前(Core i5/Ryzen 5など)」だけでなく、必ず「世代(型番の最初の数字)」を確認することが、失敗しないパソコン選びのためにとても大切です!
◆ あなたのパソコンのCPUを確認してみよう!(Windows)
今お使いのパソコンに、どんなCPUが搭載されているか確認してみましょう。Windowsなら、簡単な操作で見ることができます。
- 画面左下の【スタートボタン(Windowsマーク)】を右クリック
- 表示されたメニューから【システム】をクリック
- 「デバイスの仕様」内にある【プロセッサ】の項目を確認
ここに表示されたCPUの名前(例:Intel(R) Core(TM) i5-12400 や AMD Ryzen 7 5700Gなど)を見れば、自分のCPUの型番と世代がわかります。
◆ あなたの使い方に合ったCPUはどれ?(選び方まとめ)
| 使い方の例 | 推奨されるCPUクラス |
|---|---|
| メール、ネット検索、文書作成 | Core i3 / Ryzen 3 |
| 写真編集、オンライン会議、軽い動画視聴 | Core i5 / Ryzen 5 |
| 画像編集、簡単な動画編集、複数アプリ同時使用 | Core i7 / Ryzen 7 |
| 本格的な動画編集、高画質ゲーム、3D制作 | Core i9 / Ryzen 9 |
💡 中でも「Core i5 / Ryzen 5」の新しめの世代は、価格と性能のバランスが良く、迷ったときにおすすめの選択肢です!
✅ 失敗しないためのチェックポイント
- 「Core i〇」や「Ryzen〇」だけでなく、第〇世代(型番の数字)にも注目!
- メモリ(最低でも8GB)やストレージ(SSD)とのバランスも重要。
- 用途に合ったクラスと、できるだけ新しい世代のCPUを選びましょう。
◆ まとめ
- CPUはパソコンの「頭脳」。すべての命令や作業を処理する中心的なパーツ。
- Core i や Ryzen の「数字」が性能ランクの目安になる。
- それ以上に大切なのが「世代」!型番の最初の数字に注目。
- 自分の使い方に合ったCPUクラスを選び、世代とスペックをしっかり確認しよう。
- メモリやストレージと合わせて選ぶと、パソコンの快適さがぐっと上がります。